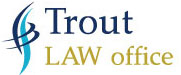性別変更規程の違憲判断 最高裁は、R5.10.25、大法廷判決で、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律の要件について、憲法13条に違反すると判断した。関連記事はこちらを参照⇒https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231025/k10014236581000.html
諌早湾開門訴訟に決着 長年地元農漁業の人たちの間で争われてきた訴訟です。
関心を持って見守ってきましたが、ようやく開門はしないという形で裁判上の決着を見た模様です。
関連記事はこちらを参照⇒https://news.livedoor.com/article/detail/23799338/
追い出し条項違法差止 家賃保証会社が賃借人と締結する保証契約における追い出し条項「賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす契約条項」
これに基づき家賃保証会社が家主に負担する賃料等の負担軽減のため、家賃を3カ月以上滞納した場合に賃借人への催促なく契約を解除できるとする同社の条項」に基づき賃借人の荷物等を運び出すことを可能とするもの。
最高裁は、この条項は、信義則に反して消費者の利益を一方的に害しているとして違法とし、契約条項の使用差し止めを認めた。ちなみに、1審・大阪地裁判決(19年6月)は条項を違法としたが、2審・大阪高裁判決(21年3月)は適法としていた。関連記事はこちらを参照⇒https://mainichi.jp/articles/20221212/k00/00m/040/010000c
DV防止法改正 以前から精神的暴力も保護命令の対象にすべきという議論があったところ、この度、法改正に向けて現実化してきた。
その他改正事項として、保護命令期間を長くすることや違反の場合の罰則が重くなることなどが盛り込まれる模様。
関連記事はこちらを参照⇒https://news.yahoo.co.jp/articles/a4ec13ffd6e425bcd0f592ced340f36c72bc9733
生殖補助医療による親子関係 2020/12/4に成立した法律ですが、近時、精子・卵子のあっせんで注目を浴びているので、掲載しておきたいと思います。
法令の概要等法務省はこちらを参照⇒moj.go.jp/MINJI/minji07_00172
法令の概要⇒https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1255891b-cd19-31fb-af25-322b913761ea
同性同士の事実婚(財産分与) 横浜家裁がこれを否定する審判をした。
事案は、事実婚(内縁)の男女と同様に共有財産の分与が認められるかどうかが争点となった家事審判で、横浜家裁は男女の内縁関係と同視することは「現行法の解釈上困難だ」として、元パートナーに分与を求めた女性側の申し立てを退けた。関連記事はこちらを参照⇒https://news.livedoor.com/article/detail/21674318/
敵対買収への新株予約権割当 TOBを仕掛けられた企業による対抗措置としての既存株主への新株予約の無償割当は、株主総会決議の効力を争う形で、会社法上の訴訟の争点の一つです。
近時では、ブルドックソース事件が有名ですが、今回報道されている新生銀行とSBIホールディングスとのせめぎ合いも注目されるところです。関連記事はこちらを参照⇒新生銀行対SBI
その後(令和3年11月29日現在)、新生銀行の動静は、SBIホールディングスに取ろうとしていた買収防衛策を取り下げるようですね(ここに至るまで政府(金融庁)が新生銀行の対応に賛成しなかったという記事が報道されていました)。関連記事はこちらを参照⇒敵対的TOBが一転
侮辱罪の厳罰化 法制審議会が、刑法の侮辱罪(現行法定刑は「拘留(30日未満)か科料(1万円未満)」)に「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を追加する案を検討しているという。
これでネット上の誹謗中傷の抑止にどの程度有効かが検証されるべきだと思います。関連記事はこちらを参照⇒法務省による侮辱罪刑法改正の方針
まだ、これからの検討段階のようですが、離婚後の夫婦間の子の養育費について、権利の強化を検討する模様。
具体的には、実務上のこれまでとの違いに着目すると(明文化のほか)、2点
(1)支払いに関する事前の取り決めを親に義務づけるもの
(2)取り決めがなくても子から他方の親へ法定額の請求を可能にする仕組みの導入
この2点をどのように規定するかが注目される。
関連記事はこちらを参照⇒養育費請求関係の法改正
後払い現金化商法 二束三文の商品にあえて高い値を付けて代金後払いで販売し、販売価格の何割かを即座にキャッシュバックする形で、現金を融通する業者が増えている。規制の穴を突いた新たなヤミ金手口とも指摘され、こうした商法は「後払い現金化」と呼ばれる。コロナウイルスによる金銭的行き詰まりに乗じた商法として法規制が望まれる。情報記事を集めて見ました。
NHKNewWeb⇒https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201230/k10012791171000.html
yahooニュース⇒https://news.yahoo.co.jp/articles/2682c0c429858627cd1568f64536505984a9f752