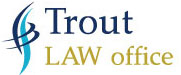最近、債務名義に基づく財産開示手続の申立てを2件ほど行った。
1件は東京地裁本庁、民事執行センター(民事21部)で、もう一件は立川支部民事第4部。
財産開示期日前一定期日までに、債務者は、財産目録の裁判所へ提出が必要となる。
財産目録の提出があると、本庁の場合は、謄写をしなければならず、司法協会に依頼するが、開示期日前ギリギリに目録調達が可能となる。
立川支部の場合は、債務者から財産目録の提出があると、申立人代理人事務所宛にFAXしてくれる。
上記1件は法人の債務者、もう一件は個人の債務者といった違いあるので、財産開示手続申立ての有効性もやや異なる。
有効なのは、法人に対してであることは間違いない。税理士などに依頼して作成してくるのが通常のよう。
個人の場合、作成してくる目録の精度を見極める必要がある。
今年の4月から施行された新しい裁判手続の制度です。実務的な視点から手続の内容を今後利用するためにまとめてみました。こちらを参照⇒第三者からの情報取得手続
R2.4.15 最高裁(第1小法廷)は、ハーグ条約に基づいて調停で合意した子の返還約束について、事情変更により合意を変更できるかにつき、初判断を示した。関連記事はこちらを参照⇒ハーグ調停合意最高裁判断
民事執行の実務のうち、強制執行について整理しました。こちらを参照⇒強制執行について
改正民事執行法の成立 5月10日、改正民事執行法が成立し(施行は1年以内を予定)、子の引渡しに関する強制執行(ハーグ条約に基づく子の解放実施も同様)、債権者が債務者の財産へ差押えをしやすくして、養育費や不法行為債権の確保ができるようにした。子の引渡しでは、これまでの執行実務では引渡の対象である子と引渡義務を負っている親がその場にいないと執行は控える(子の勝手な連れ去りと見られないような配慮)のが執行の在り方であったところ、今回の改正で、債務者の親がいない状況下でも債権者側の親が執行に同行していれば、執行官は、子を取り上げて同行している債権者である親(親権者)に引き渡すことができることにした。また、金銭債権を有する債権者が、債務者の財産状況あるいは債務者自身の収入状況を把握できないため(財産状況開示制度は設けられているが十分機能しているかは疑問視されてきていた。)、権利として有する債権が実現できないという矛盾を解消する必要があったところ、今般、裁判所を通じてではあるが、債務者の預貯金を銀行などの金融機関を通じて調査できる仕組み、債務者の勤務先を公的機関に照会できる仕組みを改正法に盛り込んだ模様。こちらの記事を参照⇒改正民事執行法の成立
以前にもリリースしたハーグ条約に基づく子の引渡の実効性が海外から指摘されていたこともあり、子の引渡の強制執行(解放実施行為)について民事執行法の改正法案が、今年4月16日に衆議院で可決され、参議院に法案が回ったようです。⇒民事執行法改正
この法改正は、国内の子の引渡しの強制執行の実務の在り方にも影響を与えそうですので、今後、成立した法案を確認し、内容をリリースする予定です。
法務省諮問機関法制審議会民事執行部会から改正民事執行法の要綱案が公表された。改正項目としては、(1)財産開示制度の強化、(2)第三者から債務者財産に関する情報取得する制度の新設、(3)不動産競売における暴力団買受防止策、(4)子の引渡しに関する強制執行の明確化、(5)差押命令の取消し、(6)差押禁止債権規律の見直し、(7)ハーグ条約に基づく子の引渡し(代替執行)の規律見直し である。
この中で、注目される改正を以下取り上げる。
1 財産開示手続は、依然から実効性が問題視されており、今回、仮執行宣言付裁判にも申立権を認めたほか、手続違背への罰則を強化した。
2 債務者財産情報として、① 登記所から債務者の不動産情報 ② 公的機関である市町村、年金機構、共済組合等から債務者の給与等の支払情報、③ 銀行等金融機関から債務者の有する預貯金、社債、株式等の情報 を取得できるようにした。
3 子の引渡し強制執行の明文化、ハーグ子奪取条約に基づく子の引渡しの規律見直し
まず、1の財産開示手続では、開示請求できる債務名義の範囲を拡大したのは、よりその実効性を高めるためと思われる。仮宣段階では現行制度上は開示請求できないのと、確定した執行力ある外国裁判所の判決、あるいは、確定判決と同一の効力のある支払督促も除外されていたが、今回の要綱案では、これらの債務名義でも開示請求できることになる。
次に、債権者が、せっかく裁判手続を通じて債務名義(強制執行可能な裁判)を取得しても、債務者が任意に金銭債務等を履行しない限り、実効性がないところ、債権者は、何とかして債務者の保有する財産を探し出して、差押えや強制執行を試みるのが一般的である。その際、これまでは、債務者のプライバシーからなかなか上記2の債務者財産情報を得ることが難しかった。そこで、今回改正では、土地・建物といった不動産について債務者名義のものを登記所(法務局)から、公務員としての給与所得、年金、共済給付金などを市町村をはじめとする各公的部署から取得できるようにする。特に扶養義務等による定期金債権については、よりその債権の確保ができるようにした。
ここで、特筆すべきは、従来、銀行等における債務者の預貯金を(仮)差押えをするには、支店名まで特定しないと申立てが却下されていたところ、今回改正では、執行裁判所が銀行等に債務者の預貯金の情報を開示することを命じることができるようにしたところです。このことにより、債務名義を有する債権者は、債務者の預貯金に対し、これまでよりも容易に強制執行が可能となることが期待できる。
3の子の引渡し、さらにはハーグ子奪取条約に基づく子の引渡しのための代替執行は、いずれも執行官の果たす役割が大きいところ、これまで、前者の国内における子の引渡しの強制執行は動産の引渡しの条文の類推適用による執行によっていたところを明文化し、かつ、執行官の権限を強化した。具体的には、従来、債務者のもとに居る子の引渡しには、債務者と子が同時存在し、一緒に住み暮らす建物に赴いて、まずは、執行官による債務者の説得により、さらには、ある程度の実力行使も可能と考えられていたものの、実務上、例えば、乳飲み子を抱えて離さない債務者の手元から執行官が強制的に子を奪い取るようなことは控えられてきた。しかし、そのような子の引渡しの在り方に配慮してきたために、強制執行が実効性を発揮して債権者のもとに子の引渡しが実現する確率は、ほぼ5割を切る状態になっていた。このことは、せっかく裁判で子の親権なり監護権を獲得しても子の引渡しが受けられない、裁判手続きへの信頼が揺らぐことや、自力救済などの横行などが危惧された。このような問題の解決を図るのが今回の改正で、執行官の権限を明確化して、必要な場合には(子の心身への配慮が前提ではある)、威力を用いたり、これまでのように子と債務者が同時存在でなければ執行できないとか、債務者と子の踏み暮らす家での執行に実務上限られていたところを、債権者が執行現場に同行することを前提に、必ずしも子の居る執行現場に債務者自身はいなくともその親族が居たり、債務者や親族の住み暮らす家だけでなく、子の居る託児所や学校などの施設(当該施設管理者の同意が必要)などでも子の引渡しの強制執行ができるようにしようとするものである。
民事執行法は、上記のように、裁判所を利用して判決や和解調書などの債務名義を取得した内容を強制的に実現するための法律であり、この民事執行法を利用して強制執行が実効性を挙げることができないと、裁判所(の手続:権利を行使するために裁判所を利用する価値があること)そのものへの信頼が揺らぎかねない。重要な役割を担う法律であることに注目していただきたい。
民事執行法改正要綱案はこちら⇒改正要綱案
法制審議会が民事執行法改正要綱を採択した。
改正の眼目は、
(1) 裁判によって生じた養育費や賠償金の支払い義務を果たさない人の預貯金などを差し押さえやすくする制度の新設
(2) 不動産競売から暴力団を排除するための新たな方策
(3) 現行法に規定のない「子の引渡し」に関するルールの明記
が中心のようです。
(1)では、債権者が申し立てれば、裁判所が金融機関や市町村などに命じ、債務者の預貯金や株式、土地・建物や勤務先に関する情報を取得できるようにする。
(2)では、暴力団組員や脱退から5年に満たない元組員▽組員らが役員を務める法人--などが不動産競売の買い受け人となることを制限できるようにする。入札申込時に組員などでないこと
を陳述させ、うその場合は刑事罰を科す。さらに最高額の入札者について裁判所が警察に照会し、組員らと認められれば売却を許可しない。
(3)では、 執行官が子の居場所を訪ね、同居の親が不在でも親権者に引き渡せるようにする。ただし、「子の福祉」の観点から親権者の立ち会いを原則とする。国境をまたいだ夫婦間の子の引
き渡し手続きについて定めたハーグ条約実施法にも同様の規定を整備する。
というものです。関連記事はこちら⇒民執改正答申
法相の諮問機関である法制審議会が、離婚した元夫婦の一方(親権のある債権者)から他方(親権のない債務者)に対する子の引渡の強制執行について、民事執行法を改正して、親(債務者)が不在のところへ執行官が出向いたときにも子の引渡を執行できるようにすることを検討していることが判った。現在の強制執行(子の引渡)では、例えば、子が学校からの帰りなど一人でいるときに、執行官が出向いて債権者である親のもとに引き渡すことは実務上しない(人さらいと同じようなものとの感覚)ようにしている。このような現行の人を対象とした強制執行には人権や感情に配慮した妥当な方法をこれまで実務を通じて模索してきた結果のもので、否定されるべきものではない。しかし、引き渡しを受ける側の親である債権者からは、なかなか自分のもとに子が引き取れないもどかしさを感じる方が少なくなかったことも想像に難くない。現在の子の引渡の強制執行の成就する確率が5割を下回っている状況には、司法が担う民事執行の実効性に危機感が見え隠れする。そのような現状に対する処方箋となるかどうかが、今回の法改正について注目されるところです。関連記事はこちら⇒子の引渡強制執行の法改正
裁判や和解で、債権者が債務者に対してせっかく執行力のある債務名義を取得しても、債務者の手元に支払財源となる財産がない場合、あるいは、債務者がそのような判決や和解にしたがって任意に支払おうとしない場合、債権者(代理人)はどうすべきでしょうか。手元不如意で開き直られると債権を回収する側は大変苦労することになります。何とか債権の回収をしようとするときに、まず、法制度上考えられるのは、財産開示手続(民事執行法第四章196条~203条)ですが、その実効性にはいま一つとされ、上記のように手元不如意で財産はないとすると、お手上げともなりかねません。また、債務者にも生活があって(どうにもならなければ破産なり個人再生という倒産手続が考えられます。)、手元に最低限の財産を残しておきたいと考えるのは 人情かもしれません。民事執行法上も債務者の最低限の生活保障のため差押え禁止財産を規定しています(動産について131条、債権について152条など)。しかし、債務者がそれ以外にも財産を隠し持っている可能性も否定できない状況も考えられます。そのような場合、債権者(代理人)は、まず、債務者が何らかの不動産財産があるかどうか、自宅が借家か本人の所有かを調べ、不動産所有が見当たらない場合には、預貯金の有無を調査することになります。ここで、預貯金の調査といっても、銀行などの金融機関が債務者の預金について任意に口座の有無、残高などの照会に応じてくれることは、顧客財産の守秘義務などから当然期待できません。そこで、債権者は、民事執行法上の債権の差押え(仮差押えも同様)を検討するわけですが、現行の裁判例では、債務者の口座について、銀行などの金融機関名のほか、その支店まで特性して執行を申し立てないと、不特定として申請が却下されてしまうのが実務の取扱いの現状です(最高裁H23.9.20決定)。他人の口座などは、従前の取引関係が債権者と債務者間であればともかく、通常は、債務者がどこにどれだけの預貯金を有しているかなど、知らない場合が多いでしょう。そのような債権回収のリスクを債権者が負っているのが現状です。これを現在検討されている民事執行法の改正では、債権者は、裁判所を通じて銀行などの金融機関に照会できるようにしようとしているようです。法改正を検討している法務省は、先の最高裁判例を受けて、本来弁済の実効性を確保されてしかるべき債権者の利益をより十全に図ろうとするものと言えます。参考記事はこちら⇒債務者口座、裁判所が特定 民事執行法改正へ